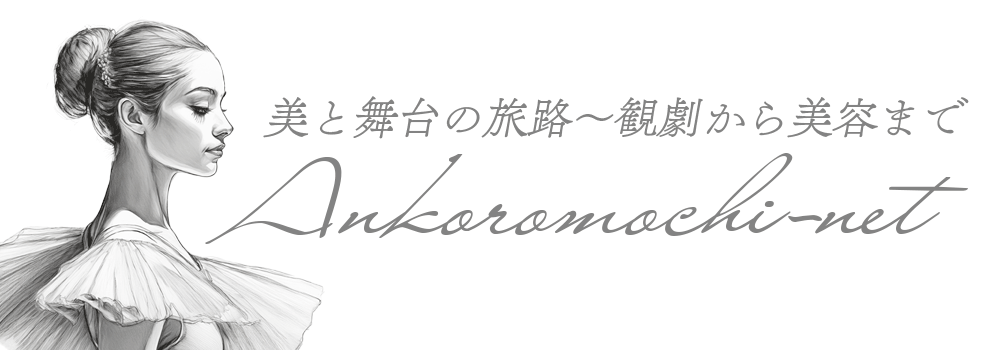パリ・オペラ座バレエ団来日公演「マノン」の初日、ドロテ・ジルベール&ユーゴ・マルシャンを鑑賞しました。
「マノン」といえば英国ロイヤル・バレエ団の十八番ですが、これはなかなか。噂によるとパリでも大層評判が良かったといいますが、それもうなずける上演でした。
おそらく「マノン」という演目の定型からは少し離れるのかもしれませんが、ファム・ファタールのマノンとそんな女を愛してしまったデ=グリューという主人公のフランスの恋愛映画を見たかのようでした。
そもそもマノンはファム・ファタールを描いた初めての文学とも言える作品で、ファム・ファタールとは男にとっての「運命の女」であり、同時に「男を破滅させる女」のことを表す。
振付のケネス・マクミランは19歳のアレッサンドラ・フェリがマノンをどう演じて良いかわからないと尋ねると、それでいいといい、のちに「マノンは自分がわかっていない子供」という解釈に辿り着いたという。
したがってマノンとは無垢で自分の魅力をわかっていないまま男たちに利用されるものと「痴人の愛」のナオミのような無意識に上位に立ち男を手玉に取る生まれながらの娼婦のアプローチがあるが、ドロテのマノンは後者だった。
ドロテのマノンは目の前のものに流される男が愛しているといえば愛が大事だと思い、裕福な生活をさせてやると迫れば宝石に目が眩む単純な女。やはり愛に生きようとしても宝石に執着を捨てきれない姿とそこからあっさりと宝石を捨てていく様は非常にムラ気で生まれながらの娼婦を思わせる演技だった。ジルベールはすでに40を超えているが、舞台上には目の前のものに目移りして目をキラキラさせる少女がいた。
ユーゴ・マルシャンのデ・グリューは一味違った解釈で、真面目というより朴訥さを感じさせた。1幕で愛に目覚め、2幕でムッシューGMの愛人になったマノンを不安そうにまるで子犬のような悲しそうな目で始終追っかけ、どんなマノンであっても自分は受け容れるようであった。(これも痴人の愛の主人公の河合っぽいと私は感じた。)
出会って恋に落ちた1幕のパドドゥなどはマノンが恋の喜びを表す解釈が多いが、ドロテのマノンは無意識に自分が手玉に取る立場であるように見えたし、ベッドルームのパドドゥもやはりマノンが無意識に上位に立っており、まるで「痴人の愛」のナオミのようだった。(ちなみにナオミもファムファタールの代表的キャラである。)囚人となり看守に犯されてしまうパドドゥ部分も驚くほど生々しかった。
またドロテとユーゴのパートナーリングが特に素晴らしかった。パドドゥでの難しいリフトもシームレスでひっかかりが全くなく、スピンや回転も速い。とりわけ沼地のパドドゥでもスピンしながらのトス&キャッチするジルベールの脱力感やが素晴らしく、30代後半のシルヴィ・ギエムのマノンの沼地と匹敵するほどのスピード感は圧巻であった。
そしてレスコーのパブロ・レガサが絶妙な小悪党感を醸し出しており、自分の妹の価値を理解しているから本気でタチが悪い(笑)とりわけ2幕の酔っ払ってのソロとレスコーの愛人のパドドゥが素晴らしかった。
ムッシューGMのレオ・ド・ビュスロルが白塗りに赤い口紅で当時の貴族を思わせる化粧がまた趣味の悪い富豪風で良かった。
ドロテ・ジルベールはこれがパリ・オペラ座として恐らく最後の来日公演になる。
10年以上前、新婚旅行先のパリでアニエス・ルテステュ主演の「椿姫」のプリュダンスや前回のコロナ禍に突入した直後の「ジゼル」など多くの舞台を見てきた。可愛らしくてどこかエキゾティックで、足の運びとスピードがモニク・ルディエールのように正確で美しくて大好きだった。
そんな意味でも記憶に残りそうな公演だった。