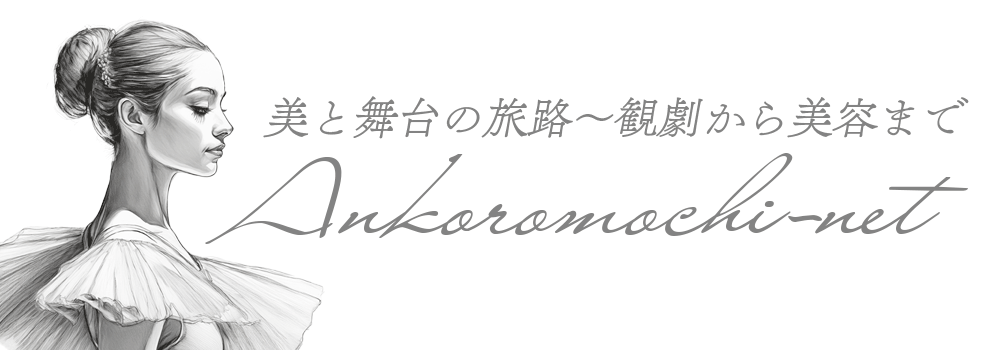エリザベート25周年ガラコンサートの興奮も冷めやらぬまま、ふと初演を見ようとしたら誰かに貸したのか、ない。
良い機会なのでBlu-rayリマスタ版を買いました。
改めて見ると、一路さんは閣下とか帝王とかいうよりも、まさにエリザベートに忍び寄る「死」そのもの。
エリザベートの心に闇ができると、どこからともなくスッと現れる。
美しくも不気味で、やはり「死」を可視化した存在なのだとわかる役作りがとても素晴らしい。
花總さんは、幼いシシィでもキャンキャンと喚くことなく幼さを表現。心の機微が分かる演技力。
高嶺さんのフランツはおおらかで歌が上手く、轟さんのルキーニは本当にイタリア人みたいで、普通っぽいのが却って狂気を感じた。
花總さんのエリザベートは最期にカタルシスを感じるかのように安堵し、死を迎え入れる。
※ところが98年、姿月さんと組んだ花總さん2度目のシシィでは、「連れていって♪」と黄泉の世界に旅立った風でした。
改めて見ると初演エリザはかなり音楽がスローテンポでゆったり。セリフも間が良く、こういうテンポ感も良いですね。
それと、一路さんはトートに対するアプローチが全く違う。
例えばドクトルゼーブルガーの「死ねばいい!」のシーン。最近は椅子に乗って手を大きく広げたり、かなり演技が大袈裟です。驚かせて死に近づけるわけではないのに、あの振りが少々違和感を覚えます。
ところが一路さんは、まるで少し死が近づいたかのように、少しゾッとするような言い方をするだけ。それに応えて花總さんも死に怯えたような表情をする。これだけでもう今、命を取られるのではないかと感じられる。
また、出て行ってとエリザベートに言われても失恋したかのように激しくガッカリしない。いま死の時ではないと悟ったようにスッと立ち去る。
宝塚版はトートとエリザベートの愛の物語がたて付けのせいか、シシィへの愛がダダ漏れているトートも多い。
エリザベートは死に対して恐れと憧れを持っていたから自ら死に近づいたり、やはり恐れて遠ざかったりもしながら死に近づくのだ。
一路さんは、影のように忍び寄る死を感じさせる。
様々なトップさんがトート像を突き詰め、それぞれの良さがありますが、一路さんのトートが唯一無二な理由はこの辺りにもある気がした。
ところで、マダムヴォルフの歌にある、
「お年寄りにはミッツィーがいるわ」のミッツィー。
ミッツィー・カスパーはルドルフの愛人で、バレエ「マイヤーリンク」や「うたかたの恋」で心中したマリー・ヴェッツェラよりもよほど深い関係にあったそうな。
現実世界で大切に思う人と、必ずしも死への道連れにしないものなんだなあ。
宝塚の「うたかたの恋」はせめて物語だけでも美しく描いており、現実を描くとやるせなく思う。